高い高いハードル、である。我が国は、国家としての決定機能を喪失した。現時点において衆参両院は過半数を特定勢力が得るには至っておらず、総裁選後の首班指名の混乱が象徴する。これは国民経済に直結する予算であったり、国家防衛を担うような重要法案でも同様のことが生じる。維新との連立は驚いたが、地方選も含め”勝率の低い出撃”を繰り返してきた者を見てきた私としては悲しみもあった。いま安定しているように見えるかもしれないが、これは一時的な安定と言わざるを得ず、解散が近づけは維新からの協力は得られないと覚悟すべきだ。小選挙区で殴り合う相手を助け、自らは死ぬ選択はいずれの党も決定しない。ゆえに、予算に対する議決や法案審議など、”安定状態にある”とは言い難い状況が継続したままである。
しかも、総理大臣をはじめ、関係閣僚の身分も安定しているとは言い難い。
解散風が吹き始めた際に、野党が結託した場合には大臣のクビが落ちまくる状況に陥る危険性は否定できないからだ。
では、活路はどこにあるのか。
衆院選において勝つよりない。
他に道はない。
いま我が国は、国家としての決定権を喪失している状態にある。
敢えて自民党の未来については論じないけれども、仮に有事でも発生したならば国民声明を守ることにすら懸念がある。
事態の重み、そして衆院選の勝利がどれほど難しいハードルであるのか、現実目線で考察していきたい。
↓読み進む前に、クリック支援お願いします。↓
↓記事が気に入ったらFBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓

![]()
バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)
不定期発信にはなりますが、チャンネル登録をお願いします。
国家としての決定権の喪失
現実問題、喪失している。
「あいつが悪い」「ここで、あの野郎が」等と言いたい方は色々といるだろうし、ややインサイダーである立場からは「あ、その部分は違う」等も言いたいが、それはまずは横に置いておいて頂く。
ない。
国会とは国権の最高機関であり、議決こそが国家の意思決定である。
敢えて自由民主党のことはさておき、我が国は、国家としての決定権が機能不全に陥っている。私は、我が国の将来の安定のため、自民党が単独で強くなることを強く期待する立場だけれども、現実問題として我が国が国家としての決定権を喪失していることは述べておく必要を感じる。
冒頭でも述べたように、衆参両院の過半数を喪失している。
私は”複雑な思い”があるゆえ、石破政権を評価はしたくないのだけれど、国会が双発機であると例えれば片肺飛行でよく飛ばしたものだと思う。本来は、あそこで行き詰まる。
まぁ、ご本人のせいだ!と言われればその通りで、私もそうは思う。
また私は小選挙区の代議士を失っており、裏金批判や無所属出馬での再処分の問題については、生身で痛みを背負っている。
(※ 当小選挙区の支部長は、正しく計上されていたため裏金はなく、勘定項目のミスで誤記載と言えるもの。派閥を背負って政倫審に臨み、それでも処分となって比例重複が許されず、僅差で敗退した。)
とはいえ、石破政権については結成直後は傀儡政権にも見えたわけで、最初で最後の解散についてはご本人の意思かは判然としない。やっとの思いで座った椅子で、無理矢理に真っ赤なスイッチを押させられたところ、椅子ごと大爆発したようにも見えた。
「支持率があがりそうだから座らせてやったのだ!」と、無派閥に近い石破氏に強く迫った者らはいたように思うし、「支持率が高い間に押せよ、さっさと押せ!!!」と。せめて予算委員会を開いて政権のスタンスを示したいと述べる総理を、羽交い締めにしてボタンを押させたわけだけど、押させた人々も一緒に吹き飛んだ事故のように感じている、ということ。
※ 地方議員である私に、国会議員と同じ感覚を持て!と読者は言うかもしれないけれども、国会の議決や役選においては市民と同じ程度の権限しか私には付与されておりません。
何回も浪人してやっと合格した医学部を、飲酒運転したから自主的に退学しろ!
明日やめろ、即時にやめろ!と言ってもなかなか辞めなかった形に見えると思うけれど、貴方がどう思おうが(私がどう思おうが)相手には相手の都合があるものだなぁと痛感した一年だった。
それはさておき、片肺飛行になってからの国会を運営してみせたのは、正直すごいと思う。
代わりに野党に何を売り払ったのか、何を飲んだのか等は気になるところだが、私にもわからない。
いずれにせよ、参院選の敗北をもって双発機の二つのエンジンは停止した。
状況は石破政権よりも実は悪くなっているのである。
これは時の政権のカラーを論じているのではなく、単に議決権の行使という一点において述べている。
議会人としては国会議員であれ市議会議員であれ私はプロフェッショナルではあるから。
閣僚を任命する権限は、総理大臣にある。
内閣総理大臣は、首班指名という手続きをもって国会の承認が必要となる。
地方議会だと役選などと呼ばれ、ようは議選である。議決が必要なのだ。
大臣の任命権は総理にある、しかし罷免する権限も国会にある。
不信任決議案などがそれで、これも議決によるもの。
予算も同様で、かつ法案も同様である。
意外に思うかもしれないが、多岐にわたり膨大な数がある。市議会であっても、です。
いずれの政権であれ、少数与党が厳しいと言われる理由はここにある。
仮に有事が勃発したとしよう、沖縄から疎開民が溢れその過程で国民の命が失われたとする。
手続きは円滑だったか問題はなかったか等、仮に必死に遂行しても不測の事態が起きうる”望まない未来”は来る危険がある。その際に大臣の不信任案を蹴り飛ばすだけの力がない。クビは飛びまくるだろう、そのたびに行政機構は麻痺する。
南西諸島に自衛隊の配備を進めたところ、北海道において謎の勢力が武力侵攻したとする。
数万人単位で自衛官が命を捧げる結果となったとして、戦闘が継続する過程において大臣のクビや総理のクビがバンバン落ちまくるのが「有事下における少数与党」である。
国民が、死ぬ。
党の存続以上に、政治家として真剣に考えるべきはここにある。
ひたひたと迫る有事リスクに対し、国家国民を守る術は何か。
結論的に言えば衆院選で勝つよりない。しかも自民単独で勝利するよりない。
非常に高い、衆院勝利のハードル。国民・参政の台頭
衆院選は、地獄だろう。
公明党の重要性を再度認識するような、そのような戦いになるのだろう。私は公明党の擁護者ではないし、そもそも【地方議員には、選挙協力がない】ため相手方にも強気には出れる。議決協力も国会が中心で(地方議会によってはないところもある。)、正直に言えば悪いのは『自分で選挙を戦う能力を喪失している自民党の国会議員』であるのだけども、26年間の温室状態の結果、恐らく自力で立ち上がることは難しい。
さらに小選挙区には、国民民主党や参政党も出馬してくる。怖いのはここだ。
ギョッとした人もいるかもしれない、しかし当たり前のことなのだ。
比例票を含め得票はそのまま政党助成金に反映される。党勢拡大の意味からも、出馬させない選択はない。
公明党の重要性を再度認識とは書いたが、それを痛感するのは国会議員だけである。
地方議員はもともと票はもらっておらず、なぜなら市議会には公明党も候補を立ててくるため創価学会は公明党の市議候補に投票するから。
自民党サイドからの論述として、ちょっとギリギリな発言をするけれども、小選挙区制は悪魔のシステムとも言える。
一位が総どりで、二位以下は落選となる。51%の支持さえ集めれば当選で、その場合は49%の民意は切り捨てて死に票となる。
何がギリギリの発言かと言えば、「公明党の推薦」がある状態下ならば、自民党の小選挙区支部長は”自動的に国会議員になる”優先的なパスポートを得ている構図にあった。
立憲や共産党のみを相手にしておればよく、正直、小選挙区における議席は『自民の独壇場』であったわけで、これは自公連立が背景にあったものだと私は感じている。つまり、自民党にあらずんば、小選挙区から衆議院議員になるのは事実上、不可能という状況にあったと述べています。これは、まぁギリギリの発言だろうなぁ。
国民民主党や参政党が台頭している。
特に参政党の存在感は大きいと言わざるを得ず、参院選においては選挙区で数万票単位で得票している。
複数人区においては実際に議席獲得までしているのだけれど、選挙区で数万を得票するのは脅威だ。どのような結果になったのかと言えば、(数字上は)自民党の票のみを吸い取る効果となっており、結果として立憲や国民が当選した選挙区は多数にのぼる。
つまり、何が起きるのかと言えば、衆議院選挙において「国民民主党や参政党」が、自民候補の票を削る効果を発揮し、自民・参政が共倒れしたうえで立憲などの野党候補が当選する可能性がある、ということ。さらに痛いのが公明党の推薦が抜けた点。
また、ぼそっと書いてはおくけれども、公明党も小選挙区に候補を擁立する可能性は否定できない。
当然勝てないだろうけれども、比例の票を掘り起こすため、特攻状態で大量に立てる選択は妥当なもの。かつての共産党方式であり、公明らしくはないけれども小選挙区を分け与えることもせず、「比例は公明」と自民は言わないのだから、死活問題として取りうる可能性は低くはない。
【自民党候補陣営】+【公明】 VS 立憲共産
【自民陣営ー国民・参政支持者】 VS 国民 VS 参政 VS 立憲共産
と対立軸が複雑化するわけで、数字上は相当に厳しい。
勝てるんだろうか、
不安にさせるような横顔の国会議員らもいる。
私は安倍元総理が大好きなので、決して批判はしたくはないが(当然批判ではないが)
安倍政権で初当選した議員らは、総じて選挙に弱い。自民党であれば勝てるという状況で選挙が繰り返されており、常勝状態ばかりを経験してきているからだ。線が細いと言ってもいい。公明票をふくめ、見える手堅い票を、計算によって得てきた印象をもっている。
私など、地方議員は(否定復活という)命綱はそもそもなく、一発勝負であり、公明などの宗教票もあてこめない。
正直に言うと死生観の部分から違いを感じることもあり、「果たして戦えるのか」と不安なのは私だけではないと思う。
国民民主党の支持者の気持ち、よく分かる。
私が政治を目指した原風景と非常に近いから。
可処分所得をあげたい、若い世代にせめてもの政策を。
麻生政権における中川昭一財務大臣に憧れ、政治の世界に身を投じた私にとっては彼らの気持ちは痛いほどわかる。
同じく、かつて我が党に票を投じてくれていた層であろうとも感じるのです。
そして、党組織ができた以上は、戻ってなど来ない票だとも覚悟している。
これは参政党にも言えることで、経済関係と保守関係の、ちょっと尖った部分などは次世代の党を彷彿ともさせる。
彼らは、恐らく戻らない。
戻る、戻らないという評価すら、ちょっと失礼だと思うんだ。
彼らにはすでに信じるものがある。
ようは、単独で選挙戦を戦う能力を喪失してしまっていた、自民党の支持部長が情けないというだけの話でもある。
ただ、ぶっちゃけガタガタの足腰だというのは、まぁ、現実だと感じる。
公明党の抜けたぶん、そしてプラスとなる票
「抜けてせいせいした」とは敢えて言うまい。共に26年も国家を運営した仲で、無駄に敵を作ることは高市政権の寿命を削る行為でもある。
ただ、自民党らしい政策が立案できるようになったのではないか、とは感じており、そこに清々しさは感じるとは述べたい。
では数字の話を。
概算にはなるし、本当の実数は誰にも分からないけれども、
仮に500万票が抜けたとする。
自民党が、自民党らしさを取り戻したこと。
そこで得られる票は、恐らく200万票ぐらいではなかろうか、と。
完全に架空の数字ではあるけれど、過去の参院比例で800万票程度を公明党は獲得していた。
直近の数字から勘案するに、選挙協力が不存在となったとして、抜けるのは最大でも500万ぐらいではなかろうか。
これに対し、増える票は200万票ほどだと考える。
同じく宗教関係の票と言えば聞こえは悪いが、創価学会とタッグを組んだ結果として”うちはいいや”となっていた保守系の宗教団体に頼み込んで選挙支援を取り付けたとして、これまた架空の数字ではあるけれども200万票ぐらいではないか、と。
神社仏閣などで、宮司さんやお坊さんが「宗教上のご利益がある!」と檀家に迫るとは考えにくい。
なんだかんだで公明党は選挙慣れしていたし、集票能力も高いというか、ようは信者数に対しての効率が高い組織であったと思うのだ。
結果、やはり数としては減少する。
耐えきれるのか、と。
大東亜戦争の、大戦末期の日本軍のように気合と根性だけでは勝てない。
前述の、悪魔のシステムと形容した小選挙区制度が実は逆に足かせともなるのであり、一位総どり方式がゆえに「左派系野党に強奪される」リスクは、現実問題としてある。
国民や参政の出馬で、自民支持層が割れ、
さらには公明が出馬した選挙区では、もはや勝利の方程式を描くことは不可能だ。
小選挙区制であるのだから、本来ならば与党である自由民主党の支部長は、それぞれの小選挙区において盤石の後援会組織を練り上げておく必要があったのだけれども、現実にはそうはなっていない。
抜けたぶんのマイナスを、入ってくるプラスで超えることは不可能だ。
このあたりは繰り返しの言葉が多くて恐縮だけれども、国民・参政が候補を擁立することは彼らの権利だ。
立憲が勝ってしまいそうだから、出馬を辞退してくれと頼み込むのだろうか。それでイエスというのだろうか。
イエスと言ってくれていたのは公明党だけで、そこで握ることは、選挙制度の硬直化という形で「与党優勢」を守ってきたわけです。
しかし、これからの時代はそうはならない。
恐らく小選挙区制度とは、公明党との連立、そして選挙協力を前提に「絶対に自民が勝つ」選挙制度の設計だったとすら感じることもある。抜けるとなって、数字を逆引きしていくとそうとしか考えられない。左派を含む野党系候補が、ほぼ絶対に勝てない仕組み。
とても安定して勝つことはできまい。
それでも衆院過半数を、自民単独で得る必要がある。
重要になるのが地方組織だ。
大阪のこと
本稿を記すにあたり、論が発散しているように感じる。
どこで書こうか、明日書こうかと悩んだ。
公明党の政権離脱であるけれど、私は事前に知っていた。なんなら交渉窓口の一つであり、第一報は私からもたらされた情報もある。別に仲良しというわけではなく、むしろ貸し借りがないゆえ協議が成立したとも言えるのだけれど(国会においても、弱みをもたない自民議員が公明党と交渉をする傾向があった)、なぜ離脱になっていったのかの経緯やメールデータを持っている。持っているというか、発信者が私なんです。総裁選直後は高市政権を支えようとしていたり、首班指名だけでも協力しようとした内部情報があったりで、破談になっていった経緯がある。
言えなかった。
このあたりは一気に端折るけれども、総理大臣への就任が足止めともなり、官房長官を含む大臣はペンディングになる。維新が協力してくれるという電撃的な情報を得て、嬉しくもあったし複雑でもあった。
余談になるけれども、前回の記事において、官房長官の就任をほぼ確定事項として喜んでいるのだけれど、この時点では公明党は自民を支えるという方針をとっていた。公明の国会議員や秘書など複数の情報より、また進みつつある政策の進捗や協力状況についても協議が断続的にあった。公明が4選挙区を喪失し、奪還を企図する大阪においても、公明側からのアクセスはあった。つないだのが、私だった。その場にいた。
大阪自民と公明は、相互に不信感もあった。都構想の住民投票もだし、4選挙区の敗北も、である。
それらを一旦は横におき、協力していきたいという申し出は先方(公明)よりなされたもの。
その翌日、
公明が連立から抜け、維新と組むことになった。
特攻機のように。
「絶対に勝てないだろう」という選挙に身を投じた者たちがいる。
堺では野村候補、市議当選から僅かな日付で市議を辞職し市長選に転出。柳本候補も、国政の公認を得ていたものを辞して大阪市長選に。のち長らくの浪人生活を強いられる。貝塚ふくめ、ありとあらゆる場所で見られた光景だ。
勝手に選挙に出たやつが悪い、自分のためだというお叱りもあるだろう。
現場で横顔を見ていた私にとっては必ずしもそうではなかったと抗弁したい。
維新が台頭し、都構想のリスクを論じるにあたり、選挙は必要だったのだ。
選挙をするには誰かが出馬せざるを得ず、無投票とはさせず、反維新の声を受け止める「依り代」として政治生命を捧げることを求められた者たちでもある。
何度も何度も負けて、それでも突撃をかまして、
しかも必要な地方議員ばかりを、若手のエースを、中堅どころを、一定程度は名を知られた者を、何人も何人も、死地に追いやってきてしまった。そのたびに組織は弱体化した。
「負け戦になるかもしれないから」と、少し申し訳なさそうに言ってくれた候補もいた。
暗に、来なくていい、泥をつけるだけだと、しかし覚悟を込めて述べていた彼ら。
その結果として二度にわたる住民投票を制することができ、私は、何度も彼らと一緒に街頭に立った。
住民投票も戦いに行った、維新と揉めている選挙区があれば駆け付けた、多くの場合は呼ばれた。対維新で、戦えるインフルエンサーが私しかいなかった時代だった。
見てきた、ずっと。
今回、連立の形となる。
閣内ではない。
解散風が吹き始めれば、維新は離脱すると思う。議決協力もなしとなり、予算はとまり法案は葬られる。
上手に見せるだろうけれど、よっぽど操縦をうまくやらない限り、任期満了直後は自民は捨てられる形になるだろう。維新にしても、せっかくの議席をむざむざ失うことは避けたいわけで、そのためには自民と戦う必要がある。必要な戦なのだ、もはや儀式かもしれないが。自民党の候補を一方的に蹂躙するという儀式。
なんなら高市早苗総理と、維新候補の二連ポスターだって作られるかもしれない。
「それは困ったな」と思うかもしれないが、困ったと思う方法を求めるのが政治交渉だ。予算も大臣人事も法案の行方も握られている以上は、相手方の言い分を飲むよりない。
維新候補が「副首都構想を、高市総理と共に推進して成立させた維新です。大阪都構想はダメになりましたが、我々は大阪に利益をもたらします」と演説している横で、「都構想と副首都構想は別なんです」と寂しそうにつぶやく自民党候補に勝機などあるわけがない。殺されることだけが決まっているゲームに臨むようなもので、武装解除させられて軍服だけ決めて穴だらけにハチの巣にして撃ち殺すような未来になることを私は恐れる。
維新側には維新側の言い分もあるわけで、この間において維新の国会議員複数とも連絡をとっており、一部は報告として提出もしているけれど、彼らだって死にたくはない。自民と戦ってきたという自負があり、自民側に”寄り添い過ぎた”と見られれば政党基盤ごと喪失するという危機感を覚えている。ゆえに、仮に協力したいと考えたとしても、強気な姿勢は崩せない。
さて、大阪においては厳しいことが起きるわけだけど、47都道府県を47で割って考えるのは選挙だと誤りだ。小選挙区で19選挙区もある。福井などは2議席しかなく、富山や石川は3。人口比で行くので、東京は爆発的に大きくて30議席。
ただ、公明の力を頼り切っていたのはむしろ東京で、東京の30はあまりあてにはできまい。人口の流動性が高すぎるため、後援会組織を結成する自民党型の選挙が苦手とする地域だ。福岡県は11議席があてられるが、佐賀は2、長崎は3である。47都道府県は、県単位では平等でもない。
地方組織に、「配慮」を求めることが増えるように思う。
それは維新にもいい顔をしないといけないし、国民にも配慮しないといけない、場合によっては参政党の協力も得たい。となれば、自民党の地方組織には「我慢」が強いられる可能性は、正直ある。野党に対する配慮は、そのまま地方組織への忍耐と同様になることもあるのだけど、
大阪の痛みは正直に言えば耐えられないレベルだろうし、もしくは19選挙区の支部長(公明の4を除くだろうけれど)に全員を打ち首獄門とすると決めてしまうのか。そんな”見捨てる”ような構図になって、それでも地方組織に小選挙区を死ぬ気で戦え!と言われても、
まぁ、ぶっちゃけやる気がどこまで起きるだろうね、という人もいる。
私は私なりに、自分の地域の支部長が大好きな部分もあったりで、とりあえずやれる範囲はやってみせたいとは思うけど、公明が抜けて参政が出馬しているような選挙区は、勝機はほぼないと思う。
政令指定都市などは、良い草刈り場になるわけで、人口も多いためで。
政党要件を満たした以上は、票=政党交付金である以上は、どこもここも立ててくる。大都市は、相当にきつい。
小泉総裁になったならば、自公+「維新」になるのではという危機感が、大阪の一部にあった。
ゆえに高市総裁候補を全力で応援していた方もいるわけだけど、逆に公明が抜けて、さらに維新に頭を下げる事態となったのは複雑な思いだ。
我々の複雑な思いなど、どうでも良いことなのかもしれない。
どうでもいい、どうでもいんだ。
国民の公益のまえに、有事における国家の安定のためには、どうでもいい軽いことなのだと思う。
悲しいマイク納めが何度もあった、特攻機を見たことはないけれど、特攻機のようだった。
少なくとも特攻機の動画を見たときの衝撃と同じ感情が私にはあった。それも含めて、きっと、どうでもいいとは言われるのだろう。
一応は、やる。
精一杯、心を奮い立たせて。
けれども、状況は想像以上に苦しいし、数字で見れば簡単にはいかない。
地方組織に”全力で”と求めるならば、最低限の配慮や筋は通して欲しいなぁとは思う。偉い人同士にはそういう声掛けはあるのかもしれないが、果たして地方側は心から駆け抜けることはできるのだろうか。
本当の終わりは、二年半後
本稿はここで終わるので、二年半後のことは別の記事で書きたい。
参院選がある。この参院選は、安倍元総理が命を奪われたときの弔い合戦の票だった。
あれから6年後の参院選となるわけで、議席数が強く出すぎた選挙結果でもあった。
普通に考えれば揺り戻しで減るのが普通なのだけど、状況はもっと悪い。
ただでさえ参院が数が足りないのに、さらに減っては連立では維持できぬ。
正直に言えば完全な下野。そして我が国は、多党化の時代を迎える。それは誰も、何も決めれない時代が来ることを意味する。ゆえに、デッドラインまでの二年半を必死に事務作業を進めるよりないと自らに課している。
とりあえず、衆院選に勝つしかない。
いつ書くかと迷っていた。
「かなり厳しい」という意見になるのだけども、
現実的な話をネット上の保守派は拒否するように感じた。当選の祝意の中では。
究極的には、衆院選で勝つしかないが結論になる。
しかも自民単独で、だ。
公明抜きで、国民や参政と戦って、それで勝たないといけない。
スローガンだけ高らかに掲げて、嘘つきになれちゃうならいいんだけれど、どうもそう上手には生きられそうにない。
国家としての決定権の喪失、ネット上でちゃんと伝わるだろうか。
その奪還作戦がどれほど厳しい戦いか、共有することは可能だろうか。
かつて民主党政権と対峙した、野党自民を支えた仲間たちは同じ熱情を持ちうるだろうか。
それなりにハードルが高いんだなと思った方は、拡散をお願いします。
個人献金のお願い~全力で活動、気持ちよく使い切りました。もうすぐ資金ショートします。
一歩、前に出る勇気。
↓応援クリックお願いします。↓
バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)
不定期発信にはなりますが、チャンネル登録をお願いします。
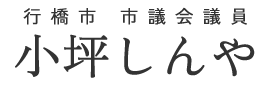



コメント (頂いたご意見は、他SNSに比較し最優先で目を通しております。)
麻生さんの戦略は…
「都市部は高市人気で票を取る」
「農村部は小泉農政(石破農政)の完全否定で票を取る」
でしょうね。
たぶんこれでうまくいく。
鈴木農相が「(都市部の米価高騰対策として)お米券を配る案がある」って言ったでしょ。
もし仮に「石破政権がお米券配る」なんて言ったら…「非難轟々間違いなし」。
ところが…高市政権だと「それもアリかもね」とか「とりあえず、くれるってんなら有難いわな」ってなる。
それから「日韓首脳会談」。
高市総理が「李在明大統領(共に民主党)と友好ムード演出」しても「ネトウヨが全く騒がない」。
さらに「高市総理が使っているバッグやボールペンが大人気」だそうな。
「高市総理が使っているモノと同じモノを使ってみたい」なんて…今までこんな現象、あったっけ?
ようするに、近々衆院選があったとして、無党派層(←日本では、これが最大勢力)の意志は…
「とりあえず、今回は高市自民にやらせてみよう」ってことです。
自公連立解消で公明党が抜けた穴の埋め方は…
都市部においては「投票者20万人のうち、無党派層は10万人。そのうち立憲、国民、参政に逃げた1~2万人を自民に連れ戻す」みたいなかんじになりそう。
とにかく私は「今度の衆院選が楽しみ」。
今まで散々言われていた「小選挙区における公明党の実力とやら」がハッキリしますからね。
もしここで「自公連立における公明党の選挙協力の力って…こんなもんだったのかぁ…」ってなったら…本当に面白いことになる。
百発百中で未来予測できる人などいませんが、「石破下ろしは失敗する。蓮舫総理があり得る。高市総理は決して誕生しない」などと言った人が、また国政予測をするのでしょうか。精度はともかく、時期的にせざるを得ないのかもですが。
過去に外しまくったことについて、何か反省や原因分析はされたのでしょうか。
「こんな不安要素がある」と言うのは、ハッキリ言ってど素人でも可能ですので、現役市議ならではの分析とは感じません。
総裁選決着直前、「誰になろうと支えていく」と宣言されてましたが、具体的に何かなさったのでしょうか。それとも、「思った通りの結果にならなかった=岸田氏の意向が反映されにくい自民になった」で、やる気が削がれて不貞腐れているのでしょうか。
ま、1票1円と投じていませんし、聞く義務もないですけど。
評論家でなく、実務者としての次の一手、注目しております。
防衛大臣に抜擢された時は何で?何でと失望されていた小泉君ですが、防衛大臣になってからは本物なのか!と言う変貌を遂げたのは元々防衛畑の方だそうですが、先生が厚い信頼を寄せておられる木原官房長官が高市政権で木原官房長官を中心とした最強防衛ラインの布陣がバックに付いているからだと思えます。小泉君はすっごいレクチャーを受けたのではないかしら。マスゴミは小泉君の事しか取り上げませんが高市さんの綿密な知識、戦略の凄さはここでも伺えます。是非御覧下さい。
🔻進次郎防衛大臣どころの話ではありません。
参政党や国民民主党へ逃げた票はもう戻ってこない旨の事を書かれておりますが、わたしはそうは思いません。それは、この二党に力を与えたのが、所謂無党派層だからです。
各種世論調査を信じるならば、直近においてこの二党の支持率は低下傾向にあり、特に連合のような支持組織を持たない参政党は大幅に支持率を落としています。
それに対し自民党は爆上がりと言って過言ではない状況にあります。
先の選挙でこの二党に投票した人の大部分は何のしがらみも無く自民党に戻ってくると思います。高市内閣がポカをしなければ、ですが。
この二党が候補を立てて当落線上に立つのは多分岩屋や石破といった党内野党連中だと思いますので、保守派にとっては寧ろ喜ばしい事かと
「国家としての決定権を喪失」
市議は、このフレーズを好まれているようです。
確かに単語としてはインパクトがあります。力のある言葉は発言者に爽快感をもたらします。
それゆえに、このような発言は、感情や別の目的が潜んでいないか、見極めなくてはいけません。
少数与党になると、国家としての決定権を失うとのこと。
私には、これがどうにも理解が出来かねます。
単独過半数の党がなければ、国家はまともに運営できないような言い回しですが、そうであれば世界中、運営できていない国だらけになってしまいます。
維新の協力は一時的な安定とおっしゃいますが、連立していた公明党も今回、離脱しました。
連立も閣外協力も信頼性に欠けるならば、単独過半数、事実上の一党独裁しかないというのでしょうか?
第一党が過半数に満たなくても、調整しながら進むものでしょう。権威主義国家のようなスピード感はなくとも、議論を通じてブラッシュアップしていく。
まさに釈迦に説法で恐縮ですが、それこそが民主主義の利点です。ようやく、まともな野党の萌芽が見えてきていますし。
それ以上に首をかしげるのは、これが「数」の話に終始し、政策などの中身が全く見えないことです。
例えば岸田政権は、安定した政権下で国民の望まないことだけを確実にやり遂げるかのようでした。
望まない決定、誤った決定だけを行う「決定権」など不要です。
それこそ、今の高市政権よりも、単独過半数の参政党や(あくまで仮定の話ですが)”立憲共産党”のほうが、国家として決定できるから良い、のでしょうか?
そうではないでしょう。
自由民主党が行うべきは、「何としても議席を増やす」ことではなく、「議席を増やせるような政策を進める」こと。
幸い、トランプ大統領と拉致被害者のご家族との面会から、高市政権は拉致問題に強い関心を持っていることが明らかです。
市議としても、政権を支えつつ状況を進めるチャンスではないでしょうか。そういった行動の結果が議席につながると考えます。
過去の政権のように、議席さえあれば良い、という考えをしていれば、再び票は離れていくでしょう。
同感です。
自民党支持者から見て、今より自民党の議席が多く公明党と連立を組んでいた石破政権、岸田政権の方が安定していたとは思えません。
何も決められない。何も前進しない。中国や韓国に対してなるべく波風をたてない。腫れ物を触るような扱い。のらりくらりと時間だけを無駄にして、自分が長く居座り続けることだけを考えている。というイメージです。
安定、安心どころか私たち国民は、何処に連れて行かれるのか不安で仕方ありませんでした。
リーダーが良ければ、部下は生き生き、伸び伸びと仕事に没頭出来るはずです。あの小泉防衛大臣でさえ立派なことが言えるようになりました。若手が育っていくと思います。
すっかり「俺たち保守派のリーダー小坪さん」ではなくて「自民党の小坪さん」になっちゃったようで今更ながら、なんだかなぁ・・・という感想です。
そもそも、自民党は保守2割、リベラル2割、ノンポリ6割の構成と言われたなかで、安倍さんが首相を務めていた時代はその2割の保守派が党内ヘゲモニーを一応は握って私たち国民の3割強を占める「岩盤保守」の支持を受けて選挙で連勝していたわけですが、2022年の7月に安倍さんが暗殺されて以降は、米ミンス党の圧力が強大だったのか岸田・石破がもともとそういう人たちだったのか、こうもアッサリと左傾化して、信じられない気持ちでした。
まあ、安倍さんの時代にも次世代の党という「保守」を謳う政党はありましたけれども、所詮は地力がなく早々に潰れましたが、今回は、岸田~石破という左翼政権が3年も続いた間に、参政党という地道に地方から積み上げてきた100%保守を謳う政党が出てきたので、いくら高市さんが総裁になっても、いつなんどき再び左翼に転んでしまうかも知れない自民党なんて、そうおいそれと以前のようには信用できない、となっている保守派の人が、今は多くなっていると思います。
福岡の武田良太という方も、保守風味を匂わせながらも、結局のところ岸田・石破あたりとつるんでいた人、という感想しかなく、今となってはもう二度と議会に戻って欲しくないなあ・・・と。
まあ、いろいろと想定外のことが連続し、見通しの悪い状況ですからね。
政治家の一寸先は闇と言われるように、些細なことで政局は激変にも。
現時点で先を読むことは、あまり意味のないことに思えます。
一つ言えるのは、新しい風が吹いて来たことでしょう。
この風に乗れる人は、新しい時代に向かえます。
新年早々にも、大きな風が日本に吹いて来るとも。
安倍晋三氏、中川昭一氏御霊の神風なのかも知れません。
.